| 棟梁 沖野 誠一 |
|
|||||||||
|
|||||||||
| 土 佐 の 自 然 素 材 |
|||||||||
| 土 佐 和 紙 | 土 佐 の 木 | 土 佐 漆 喰 |
 |
 |
 |
| 土佐和紙は、コウゾの樹皮を原料とします。土佐の豊かな自然から育まれました。 →続きを読む |
土佐の大自然で育だった樹木は、厳しい気象条件を生き抜いてきました。 →続きを読む |
土佐漆喰の風合いは、壁を触ると人間の肌のような風合いがあります。 →続きを読む |
| 環境を真剣に考えなければならない時代がきました。 そのためには、輸入材や集成材ではなく、地域で伐採された国産材(地場材)を使うことが一番です。 太陽光発電や高断熱構造から二酸化炭素削減することもできますが、大金を叩いてまで買い替えや購入する必要があるのでしょうか。故障や劣化などで消耗して耐用年月を過ぎれば、モノはゴミに変わります。リサイクルや再資源化されても、輸送費や処理費用に相当のエネルギーが使われ、膨大なコスト高になるでしょう。 これでは、大量生産・大量消費・大量廃棄に歯止めがかかりません。 エネルギー消費の抑制は、伐採から製材、輸送コストまで考慮して国産材(地場材)で建ててこそ、環境に配慮した本物の住いといえるのではないでしょうか。食材を産地や農法で選ぶように、毎日生活する家こそ産地履歴が必要なのです。 |
| 木を切り出した森林に再び植林することは、木材が唯一再生できる健全資源であることがわかります。化石資源や鉱物資源は確実に枯渇していきますが、植林システムは自ら資源を作り出すことができます。地球環境に負荷をかけない植林循環により持続可能になるのです。 木材は、鉄やアルミニウムなどに比べて製造に必要な消費エネルギー量が低く、二酸化炭素の排出量を少なくすることができます。森林から木材を生産するのに消費エネルギー1t当たりに換算すると、鋼材は23倍、アルミニウムは290倍になります。 また、同じ面積の住宅を建築するときに発生する二酸化炭素の総量は鉄筋コンクリート造や鋼構造建築物の約2分の1から3分の1に抑えることができます。つまり、木材に代わる他の建築資材を使えば、地球環境への影響は大きくなりますが、木の家を建てることで消費エネルギーを抑制することができるのです。 わたしたちは山元に出向き、森を育ています。住い手と産地をつなぎ、顔の見える関係づくりをはじめました。 また、木の伐採から建築の流れを明確にすることで、山にお金が戻る仕組みづくりを考えます。そのためには、両者が森に感謝し合う気持ちを持ち、川上と川下が信頼関係を築いて山を育ていくことが大切です。 |
| 地球は今、どんどん暑くなってきました。 1997年の京都議定書では、森林が二酸化炭素の吸収源として重要であることが認識され、温暖化問題に世界規模で取り組んでいます。森林は二酸化炭素の貯蔵庫です。日本の森林には約14億tの炭素が貯められ、年間2700万tを吸収しています。 杉人工林は50年間で1ha当たり、約170t貯蔵すると推定されています。現在の住宅は20〜30年で建て替えられますが、 二酸化炭素を貯め込んでおくためには、100年くらいは住み続けられる木軸組工法住宅をつくることが必要です。 人工林の場合、まず苗木を山に植えます。杉や桧は1ヘクタール当たり、3,000本から5,000本植えます。植えた木は手入れが必要になります。植えた苗木が下草に負けないよう下刈りを行い、枝打ちや間伐作業を繰り返し節の少ない丈夫な木を育てていく のです。そのためには、地域で育った木を使います。 家に屋根があるように、木も大きな根を張り風雪に耐え、50年ほどかけて地域の気候風土に合う木材として成長します。 近くで命を育んだ木で造る家で暮すこと、これこそが、最高の健康志向と言えるのではないでしょうか。 また、住宅として寿命を終えて解体されても、使用された木材は赴きある古材として再び建築材として利用されたり、砕いて パーティクルボードの原料として家具に利用されたり、紙やパルプの原料となります。 最終的には、燃料として燃やされ二酸化炭素として大気中に戻るか、腐朽して土壌に還ることになります。 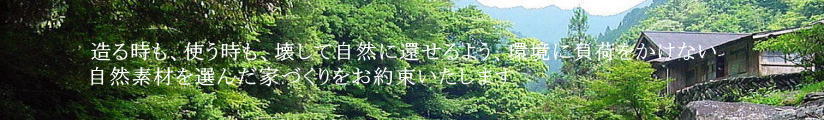 |
| 〒781-0112 |
| 高知県高知市仁井田3353−4 |
| 沖野建築 |
| 棟梁 沖野誠一 |











